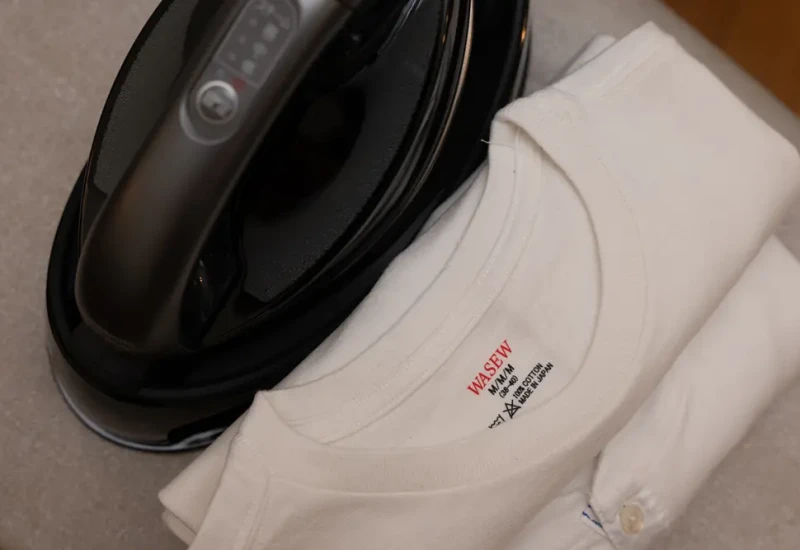S-Works Tarmac SL8

Specialized社のフラッグシップであるS-WorksのレーシングバイクTarmac SL8について

はじめに
生活環境の変化で撮影に行く時間が取れなくなって以来ブログを放置していたのですが、元々紹介したかった記事があるので時間を見つけぼちぼち紹介していければと考えています。
今回は昨年夏に紹介したSpecialized Tarmac SL7から乗り換えたS-Works Tarmac SL8について紹介します。本来はもう少し乗り込んで、サイクルウェアやビンディングシューズやヘルメットなどと一緒に紹介したかったのですが、撮影時間が取れない事があり、自転車のみの写真となっています。
Specialized Tarmac SL7からS-Works Tarmac SL8への乗り換えは23年の8月に行なっています。
※写真は23年の8月に軽く乗った際に撮影した写真がメインになっています。
Specializedのロードバイク
Specialized社の商品は、完成車とフレームから組み合わせたいパーツを選んで組む完組と言われる商品構成になっていて、私の購入したSL8はフレームを選んで組んでもらった完組です。ただ、Specialized社が完成車に組んでいるパーツをフレームを選んで組んでもらっているので完組とは言え完成車に近いセミコンポーネントと言った構成になっています。
購入時の商品構成が、コンポーネントがShimanoかSRAMのコンポーネントの選択と完成車のフレームカラーとフレームのみの購入に用意されているカラーがあり、フレームのみの購入に好みのカラーがあったので完組にて購入しています。
元々、ロードバイクは一般的な趣味としての楽しみより、トレーニングギアとしての意味合いが強く、仲間とツーリング的なライドや競技など、ロードバイク愛好者が行っているような使い方とは異なる使い方をしています。白を選んだ理由は、道が空いている地方の国道を夜走る事が多く、暗い道でも視認性の高い色と考えた結果が艶感のあるホワイトマーブルという色を選択した理由になっています。
購入目的はトライアスロンの挑戦
本来、私のような使い方ではなく、競技をしている方向けのロードバイクがS-Worksのロードバイクになります。Specializedのロードバイク自体がかなりの高性能バイクであり、私自身が使うにはオーバースペックな面もありながら、さらに高性能なS-Worksの最新モデルであるSL8購入したきっかけが、トライアスロンにチャレンジしようと考えた事がきっかけとなっています。
トライアスロンにはクラスのようなものがあり、私がチャレンジしようとしたクラスがオリンピックディスタンスと言われる
- スイム 1.5km
- バイク 40km
- ランニング10km
の3種目の距離になっています。
トライアスロン挑戦の理由に、日々7kmから時間のある時は12Km程度の軽いランニングを行い、夜30km弱から時間のある時は70Km程度の距離をロードバイクで走るといった軽い運動ながら、トライアスロン競技の2種目を日常的に行っていた事で、ここにスイムがあればトライアスロンに参加して完走出来るのでは?と考えた事がきっかけになっています。
トライアスロンには専用のTTバイクと言われるものもありますが、そこまで本格的には考えなかった事と、競技専用となってしまうので、普段トレーニングとして乗ることも難しいということや、トライアスロンに興味を持ったタイミングがSL8の発表と重なり、SL7やディバージュを購入したショップさんからSL8発売の話をいただき、オリンピックディスタンスの完走目的ならロードの方が使いやすく、SL7よりSL8の方が同じ距離の運動量でも疲労が少ないのでトライアスロンでの使用に向いているといったショップのスタッフさんからのアドバイスもありSL8の購入につながっています。(私のように高齢に近い歳からの挑戦で目的がショートディスタンスの完走ではなくミドルやロングディスタンスへの参加や上位を狙う方は違った選択種があると思います。)
実際には、購入以降、公私共に時間が取れなくなってしまい、トライアスロンの計画は一旦保留となり、ランニングやロードバイクに乗る時間も取れないままになっています。
時間的な余裕が出来たら、軽いランニングやライドを再開して、いずれはオリンピックディスタンスのトライアスロンにチャレンジしたいという目標とモチベーションを保てたらと考えこの記事を書いています。
S-Works Tarmac SL8は最新のSpecialized社のレーシングバイクであり、過去のVengeのイメージから空力性能への期待が大きかったのですが、製品が発表されたら、空力のコンセプトが期待されたものではなかった事もあり評価が分かれており、興味はあるが実際どうなの?というイメージ(私の勝手な想像ですが)が出来上がっているのかなと考え、実際購入して少ししか乗れていませんが良いロードバイクなのでその辺りを記事で書ければと考えています。
S-Works Tarmac SL8について
SpecializedとS-Worksの違いは、Specializedは元々高性能なロードバイクやMTBなどを製造するメーカーであり、レースなどで使われるプロ用モデルをS-Worksという別ブランドにして販売しているという表現が一番わかりやすいのではないかと思います。
SpecializedとS-Worksの関係はドイツの自動車メーカーに例えるとわかりやすく、BMWならM社、アウディならRS、メルセデスベンツならAMGといった、メーカーが持つワークス体制でレース用に開発されたGTクラスのレーシングカーを、市販車用にして一般に販売している別ブランドのイメージになります。自動車と異なるのは、自動車はレーシングカーでは公道を走る事が出来ないので市販車としての販売は公道を走れるようにした状態で販売されており、実際のレーシングカーとは異なるものになっています。自転車はそのまま販売してくれるので、アマチュアでもツールドフランスを走るプロが乗るものと同じロードバイクを購入することが出来ます。
Specialized Tarmac SL7とS-Works Tarmac SL8はどう違い、私自身が乗り換えた事を踏まえ乗り換える価値があるのかという事に軽く触れてみたいと思います。
S-Works Tarmac SL8が発表されると、良くも悪くも話題になりましたが、ロードバイクに関わらず、現代の技術の進化は凄く、実際に違いを体感出来るのかといったら、YESでもありNoでもあります。これはiPhoneなどの最新モデルの買い替えが必要か?という状況にも近く、結局使う方がその性能を必要と考え欲しているか?という事が結論になります。
SL7から最新のSL8の進化もあるのですが、Specialized とS-Worksの違いも大きいので簡単に触れてみます。
このブログがロードバイク専門ではないのでロードバイクに詳しくない方が見てもなんとなくイメージできていただけたら幸いです。
Specialized とS-Worksの違い
- フレーム Specialized とS-Works共にカーボンであるがS-Worksの方がグレードが高い(軽さや強度など)
- コンポーネント(ギアやチェーンやブレーキなど)Specialized とS-Works共にShimanoの電動であるがSpecializedはアルテグラというグレードでS-Worksはデュラエースというグレード。両者の違いも軽さと操作感による違い、デュラエースにはパワーメーターという走行能力を測る(自身の脚力)機能がついています。(SRAMも同様)
- ハンドル Specialized とS-Works共にカーボンであり昨今のトレンドでもある空力化がされています。SL8で使用されるハンドルの方が軽量かつ空力性能が優れています。
- シートポスト Specialized とS-Works共にカーボンであり昨今のトレンドでもある空力化がされています。SL8で使用されるシートポストの方が軽量かつ空力性能が優れています。(52サイズと54サイズで使用出来るシートポストが変わるのですが電動シフトのバッテリーがシートポストに干渉するのでシートポストのサイズ合わせがシビアになります。)
- シート Specialized とS-Works共にカーボンでありSL8で使用されるシートの方が軽量。
- ホイール 昨今のロードバイクのトレンドで空力を意識した深いリムとディスクブレーキによりカーボンホイールとなっています。こちらもSL8で使用されるホイールの方が軽量かつ空力性能が優れています。
- タイヤ Specializedがチューブレスレディに対して、メンテナンス性などを考慮し対応はしていますがクリンチャー(チューブ)を推奨しているので、クリンチャータイヤを装着しています。(定期的なシーラントの注入などチューブレスレディはメリットもありながらメンテナンスではまだまだアマチュアが軽く乗るには敷居が高い面もあります。)タイヤもSpecialized とS-Worksでは異なるグレードのものを装着しています。こちらもS-Worksに装着されるタイヤの方が高性能で軽量です。
上記に述べたわずかな違いの積み重ねが軽さや空力性能の差となりその数値上の軽さや、空力性能の恩恵は乗り比べると違いとしてわかります。速さもですが、機械的な精度が上がり物理的な違いを体感として感じるので、乗り比べるとその差は感じ取れます。
コンポーネントは、吊るしで組まれたロードバイクを購入する際の違いであり、フレームを購入し、コンポーネントやパーツを好きなパーツで組む事も可能なので、人によっては違いはフレームのみとなる場合もあると思います。
この、使用されているパーツの違いやグレードが価格差になっています。(昨今急激な円安で価格が高騰しているのは残念です)