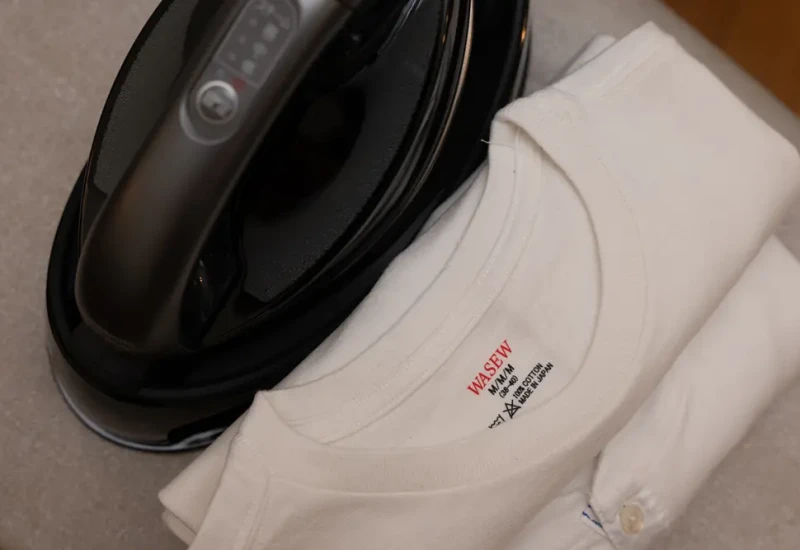S-Works Tarmac SL8

乗り手に寛容であるという進化
空力性能、軽量化、乗りやすさ、乗り心地、疲れにくさのバランスをうまく取ったのがこのSL8の進化であり、そのことにより走破能力も大した事ない私のような単なる愛好家にとっても、それなりに走れてしまうバランスと許容範囲を広く取り、乗り手に寛容になった事がSL7からSL8への進化と感じています。
SL7は競技用として真っ当なロードバイクで、乗り味も硬く、乗り心地もハードで、例えると、サスペンションを固めたチューニングカーであり、レーシングカーで言うと、路面ミューが高く路面が綺麗でタイヤの設置面を確保しやすいFSWなどのサーキットを走るセッティングのマシンで路面状況がある程度良好という前提に合わせたスイートスポットを絞ったイメージです。
SL8も競技用としては真っ当なロードバイクですが、チューニングカーで言うと、リアのトラクションをもう少し活かしたいから、リアを緩めセッティングを煮詰めたチューニングカーであり、レーシングカーで言えば路面が不安定なニュルブルクリンクのノルトシュライフェを走る様にサスペンションを緩めタイヤの設置面を確保した、不確定で変化する路面状況に対し、スイートスポットを広く寛容に取ったレーシングカーと言ったイメージです。
過去に経験した自動車レースと共通する部分
※ニュルとFSWの違いに、15年ほど前にニュル24時間のポルシェのワークスを率いたマンタイレーシングが、市販車用のパーツを販売したのですが、知人がこのマンタイレーシングのサスペンションを入れたGT2を所有しており、少し乗らせていただいたのですが、FSWを走るポルシェのチューニングパーツに見られる高いバネレートで締まったサスペンションのイメージで乗ると肩透かしを食う柔らかさでびっくりしました。販売代理店の社長さんもご一緒していたので話を伺うと、このサスペンションの柔らかさが、当時ニュル最速を出すために路面変化やGの変化でもタイヤの設置面を確保するために煮詰めたセッティングと聞いてびっくりしたのを思い出し、車とは関係ないはずのロードバイクの足あたりの感触とイメージが被って記事に書いています。
自動車のサスペンションセッティングに共通する乗りやすさ
※自転車とは関係ないのですが、私自身15年ほど前、ポルシェのGT3RS(Type997)を所有し、市販車で走れる草レースに出ていた事があり、吊るしで、アライメントをいじるくらいの感覚で乗っていました。サスペンションのセッティングはメカニックさんにお任せでしたが、タイヤの焼け具合を見て乗った感覚を伝えメカニックさんが提案する弱アンダーで乗りやすい車両にしていました。
当時のポルシェのアライメントの概念に、トーとキャンバーが、トーインが控えめで、フロントのネガキャンは出して、リアのネガキャンは控えるセッテイング。フロント寝かせてリア立てるセッティングがあたり前でした。当時のメカニックさんがこのセッティングは空冷時代のポルシェの概念で、曲がらない車を曲がりやすくする少しオーバーステア気味のセッティングだから水冷でシャーシの性能が上がり進化したタイヤ性能を考えたら、弱アンダーのセッティングの方が乗りやすいと言って、少しトーインを付けて、フロントのネガキャン控えめ、リアのネガキャンを付ける、フロント立てて、リア寝かせるセッティングにしてくれてこれが弱アンダーで乗りやすく、タイムも出しやすかった事を思い出しました。この概念は、その後の991型や992型で採用されています。
このアライメントの意味にポルシェ911のリアエンジン、リアドライブという車の後ろ側に重量が寄る構造的な問題を解決する事があります。当時のポルシェはレースをするオーナーには縦車と言われていて、コーナーの立ち上がりと侵入のブレーキングで勝負する車でコーナーの旋回スピードでタイムを稼ぐ車ではなかった事があります。

※当時のRSのバネレートが吊るしで6Kg、Sタイヤ用に合わせたバネレートが14Kg、スリックタイヤなら22Kgのバネレートとなっています。私は吊るしで乗っていたので、6kgのバネレートでしたが付属するスポーツモードというアクティブサスペンションにより車高を下げ、バネを縮めてバネレートを上げ、減衰も上げるというスポーツモードでサーキットを走り、トラコンを切り、認証のラジアルであるピレリのP-ZEROコルサを履いていてFSWの周回ラップは1分56秒台のタイムでした。ジムカーナをやっていた知人はインチダウンをして18インチのSタイヤRE55を履いて内装全部剥いで軽量化しパーツを変えて1分53秒台で走っています。タイムは今考えると大したタイムではないのですが当時のタイヤではそれなりに早かったタイムです。その後クムホのイン⚪︎キスポーツラジアルタイヤ(スリックのパターンに一本の縦溝というほぼスリックタイヤ)が出たりタイヤ性能が全体に上がりラップタイムが上がって行きますがこの時期はレースを辞めていたので、後のタイヤの進化は体験していません。
わかりやすいスペックではない価値は評価されない?
※997時代(前期型)に評論家やメディアは、GT3とGT3RSの比較記事を行い、GT3クラブスポーツをベストバイとしてGT3RSに批判的な意見を述べ記事にしていました。その理由が、RSとの販売価格の300万の差額を正当化する理由がない的な内容でした。本来車の評論をスペックなどで語るならリフトアップして車の細部を見るなどするのが当たり前ですが、評価が、ぱっと見の高価なカーボンのウイングなどの話になっていて、本質であるこの300万の差額を感じるのが、シャーシの剛性とサスペンション周りの設計やパーツの差でありその効果が走りのどの部分に影響するかということが見抜けていませんでした。
RSとGT3の開発思想に911のNAエンジンの高性能版がGT3であり、そのGT3をよりレーシングカーに近づけたものがRSとなっています。このレーシングカーに近づけたという事にGT3のアライメントの調整範囲よりRSの方が調整範囲が広い事(レーシングカー同様シムで調整可能です。これは964RSとカップも同様でポルシェの開発思想の伝統)、ブレーキキャリパーの重心が低い事やアップライトの違いなどがあり、より足下重量の低重心化をしてます。ワイドトレッドで剛性の高いターボボディによる重量増を軽量化で補うためのカーボンパーツやリアウイングの大型化や空力を考えたフロントスポイラーのパーツと合わせている恩恵が、同じような能力のドライバーがコーナーに入ったとき、RSの方が先に向きが変わります。この先に向きが変わるという事の大きさが当時の評論家には理解できなかったのでしょう。(コーナーの出口で先にアクセルを開けられるという恩恵がいかに大きいかという事とシャーシの剛性とリアのトレッドがワイドになっていることで横にGが残っていてもトラクションをかけやすい事)
あと、当時のRSはルマンなどを走るRSRのベース車両で、GT3はカレラカップ用のGT3カップのベース車両であるのでその差は歴然ですがこのあたりの成り立ちも見落とされていました。
ポルシェも996や997時代のGT3とGT3RSの違いに、エンジンなどベースが同じで数値上のスペックの差はなく、よりレーシングカーに近い仕立てとレーシングカー的な調整幅の広さという一般にはわかりにくいマニア向けで必要とする人が選べば良いというスペック的な差を売りとしていましたが、評論家やユーザーがその差を感じ取れない事に気がつき、その反省からか後の991、992のGT3とRSはだれが見てもわかる、エンジンの性能差や、空力パーツや盛り盛のカーボンパーツ、ニュルのラップタイムなどの差を付けて現在に至っています。
その後に販売された991以降のRSは凄い車ですが、楽しめるスピード領域が高くなりすぎて、サーキットを走らせないと楽しめない車かなという印象です。私自身もレースをしなくなり、RSはバッテリーをあげないために動かすという使い方になり乗る機会が減った為手放してしまいます。その後所有した991はターボSを選びRSのようなレースを楽しめる面白さはないのですが普段使いしやすさとポルシェが持つ機械精度の高さを凝縮した仕様に満足しています。(RSは所有する価値や満足度は非常に高く価格以上の価値は感じ取れると思います。ポルシェの面白さに高級車ではなく高性能車両であるという事があり、この要素が精度の高い道具を所有し使いこなすという楽しみに繋がっています。)ただ991以降一点退化といっては語弊がありますがここは戻して欲しいという仕様があるのですが、この事も評論家やメディアは見抜けていません。(機会があれば記事にします。)
話が脱線してしまいましたが
スペックがわかりやすい高性能は、メディアで取り上げられやすく絶賛されやすいのですが、実際にその恩恵を受ける方がどれくらいいるのか?という事。分かりにくい進化は評価され難かったり、場合によっては批判されやすいという事。この事が車だけでなくロードバイクの話題や発売時の記事にも感じられ、所有した車の時感じたメディアや世間の反応を交えこの記事を書いています。
今回脱線しましたが、機会があればポルシェの記事も書いてみたいと考えています。